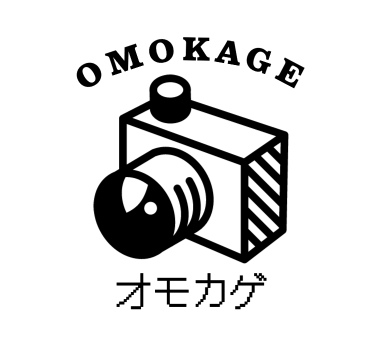セルクナムとの出会い
一九六六年、ロラ・キエプヒャがハインの詠唱を録音した時には、
ハインの祭典がすたれてから三十年以上の時が経っていた。
アン・チャップマン『ハイン 地の果ての祭典』
訪れた本屋の平積みの中から、この表紙を見つけた時は思わず声が漏れそうになった。それはセルクナムという南米パタゴアニの最南端にかつて存在した民族を写したもので、僕はその表紙と全く同じ写真の絵葉書を持っていた。
以前、ブルース・チャトウィンの『パタゴニア』で描かれた行程をトレースするためアルゼンチンとチリを訪れた時、まずはブエノスアイレスの自然科学博物館へ向かった。目的は南米大陸が北米とは孤絶していた時代に生きた不思議な動物たちの化石を見に行くためだった。ミロドンやメガテリウムという全長5メートルを超えたという大ナマケモノや、グリプトドンという全長2メートル超のアルマジロなど、今から一万年ほど前までに生きた非常識なまでに巨大な生物たちの化石はいつまで見ていても飽きなかった。
そんな展示に混じって、白と赤の横じま模様の全身タイツを着た数名の男女が不可思議な踊りを見せるインスタレーションが、展示スペースの一角で、粗末な布スクリーンに投影されていた。英語の解説がないため、詳細はわからなかったが、それはかつて南米パタゴニアに存在した民族の風習をアートとして表現したものだという。
「ヤーガン?」
近くにいた館員に、『パタゴニア』を通して知っていたパタゴニア最南端の先住民族の名前を挙げて聞いてみた。
「ノー、セルクナム」
そういうと彼は僕を館内の売店にまで連れて行ってくれ、一枚の絵葉書を見せてくれた。そこにはインスタレーションに登場していた全身タイツ姿でポーズを取っている姿が古ぼけたモノクロ写真になっていた。裏面にはスペイン語の説明に併記して、英語で「セルクナム(Selk’nam)族における、通過儀礼ハインの際のボディペインティング」と書かれていた。
「これは売り物?」
館員は頷き、これが最後の一枚だと言った。アルゼンチン最南の町で南極観光の起点でもあるウシュワイアから取り寄せた絵葉書だというが、あっという間に売り切れたという。他の写真を使った絵葉書はウシュワイアの「地の果て博物館/ MUSEO DEL FIN DEL MUNDO」に行けば手に入るだろうとも教えてくれた。ウシュワイアにもこの後で行く予定だったから、好都合だった。
それがセルクナムという不思議で、そして悲しい人々の存在をはじめて知った経緯だった。
火の島の先住民セルクナム
一八八九年、マゼラン海峡沿岸部で十一人のセルクナム人がさらわれた。ヨーロッパへ連れ去り、食人種として見世物にするためだった。彼らはパリで檻に閉じ込められ、飢えにさらされ、その上で生肉を投げ込まれた。食人癖があるように見せかけて大衆を騙そうとしたのだ。
p45,『ハイン 地の果ての祭典』
南米大陸の南端からマゼラン海峡を超えた場所に点在する島々を、フエゴ諸島という。1520年の航海でマゼランが、後に自らの名が付けられる海峡を通過した際、島から焚き火の煙を見たことから、スペイン語で火を意味するフエゴと付けられた。
アフリカで生を受けた人類が、ユーラシア大陸を東進し、氷河期の影響で陸地となっていたベーリング海峡を渡り、北米、さらには南米へと至る、長い長い人類の移動の旅のどん詰まり、そこフエゴ島だった。この先には人間生活には不適で、ペンギンやアザラシが暮らす南極しかない。
本書『ハイン 地の果ての祭典』の著者アン・チャップマン女史は1960年代ごろから、まだ当時は僅かに残されていたフエゴ島のかつての姿を知る先住民たちとの生活を交流を通し、その散り散りになっていた文化の欠片の収集と再構築を、民俗学的アプローチで開始した人物だ。ここでは彼女がソルボンヌでレヴィ=ストロースに学んだ経験があるということよりも、彼女が女性であるということを強調しておきたい。本書を読むほどに、彼女が女性であるという当たり前の事実は、その研究においてほとんど決定的なまでの役割を果たしていたことがわかる。
フエゴ島には南部の島々やホーン岬など海岸部で暮らした遊漁民ヤーガン族をはじめ、それぞれ独立した言語を話す計4部族が暮らしていた。セルクナムは主に内陸部に暮らす狩猟部族で、他と比べて好戦的として知られていたという。そんなフエゴ島の先住民は今ではほとんど絶え、純血に限れば、2017年現在、最後のヤーガンとしてし知られる女性ただ一人が残されるだけになっている。理由は他の新大陸の先住民が辿った歴史と同じく、入植者が持ち込んだ銃や伝染病といった西洋文明からのありがたくもない贈り物のせいだ。19世紀半ばには4000人はいたとされるフエゴ島の狩猟民たちも、本書で詳細に検証される1930年頃には100人ほどに激減している。
そしてセルクナム族の特異な精神世界の中枢をなす祭典ハインもまた、1930年代前半には継続することが不可能な状態に陥っていた。
本書『ハイン 地の果ての祭典』は、1923年に開催された祭典ハインに参加が許されドイツ人の人類学者で神父だったマルティン・グシンデ(事実上は彼が祭典のスポンサーだった)が残した貴重な記録と写真を主たる骨格に、著者が1960年代にはまだ僅かに残っていたハインに参加経験のあるセルクナム族との交流を通して得た見識を加えることで、今はもう幻となった民族の、幻の祭典を蘇らせる試みと言える。
通過儀礼としてハイン
祭典は、クロケテンと呼ばれる成人候補者たちが、ショールトという「精霊」に拷問を受ける儀式で始まる。その終わりには、大人たちが精霊の仮面を取るようにクロケテンに命じる。すると彼は、自分と同じ人間の顔を目の当たりにするのだ。
p20, 『ハイン 地の果ての祭典』
セルクナム族にとってハインとは、平たく言えば、通過儀礼である。
まだ未熟なセルクナムの少年たちが、この儀式を経験することで一人前の男になる同意を共同体から得ることを目的としている。そしてバンジージャンプやウォークアバウトといった通過儀礼と同じく、それは少年を成人に成長させるという個別的な目的のためだけでなく、彼を大人として迎い入れることで共同体そのものの強化を図るという意味もあった。そのためには、本来は明確な区切りなどない少年から大人という成長の連続性の中に、人工的な境界面を設定する必要がある。今までいた場所から、新しい場所へと移行するために必要な日常では未体験の領域を共同体は用意する必要があった。この未体験の領域こそが通過儀礼だと言え、多くの場合はそれは少年が大人になる変移を指す。
これは少女が大人になる際、時限式に初潮という生理現象が訪れることとは対象的に、男は共同体の助けがなければ大人になれないという事実の裏返しでもある。
初潮を迎えた少女が隔離され、共同体の女たちから大人になるための手ほどきを密室空間で説かれるという初潮儀礼の形式が多くの地域や民族で共通するのは決して驚くことではなく、ある種の文化的自然状態とも言える。セルクナムの社会でも初潮を迎えた少女は男たちから厳重に隔離されるが、こういった初潮儀礼はもはや文化の問題としてはくくれないほどに、世界に広く分布している。その一方で、少年を大人にするための通過儀礼には、それが属する共同体の思想や成り立ちが色濃く反映されることになる。故に、少年のための通過儀礼はその文化を端的に表すことになる。
セルクナムの通過儀礼ハインが、他に例がないほどの奇怪で鮮烈な理由とは、その社会が保持していた文化の反映でもあった。
母系社会への拒絶と畏怖
こうしたこと全てを、そしてホーウィン時代のハインにまつわるその他もろもろの出来事を、未来永劫に渡って男たちの記憶の中だけに留めておくよう、最大限の注意を払う必要があった。決して女たちには知られてはならないのだ。
p192, 『ハイン 地の果ての祭典』
『ハイン 地の果ての祭典』の著者アン・チャップマンが女性であることを強調した理由は、セルクナムの文化の中枢を形成する民族神話に由来する。そしてその神話的世界の維持継続という目的が、通過儀礼というハインの裏側に隠れた、共同体のためのハインとしての役割を担っている。
ハインとは単に未熟な少年を大人に鍛えるためだけのものではなく、その過程で男だけにしか共有が許されない秘密の継承の役割もあった。その秘密というのは、端的に言えばハインの嘘である。そしてハインの嘘というのは同時に、セルクナム神話の嘘でもあった。
セルクナム族は徹底した父権制社会を築いていた。その社会において実権を持つのは男であり、女は常にその支配下に置かれるべきだとされる。その一方的な支配体制は、同時にその対極に位置する母権制をひどく嫌悪し、そして恐れることを必要とした。本著の中ではその関係性を資本主義と共産主義の思想対立に重ねているが、まさにセルクナムの神話の成立背景には、資本主義の絶対性を唱える人々や、共産主義の完全性を説く人々と同質の作用が働いている。つまり自分たちが信じる思想の正しさを訴えるためには、それを脅かす仮想敵を作り出し、その不備を徹底して攻撃しなければならないということだった。
父権的セルクナム社会において、それは母権的社会に相当する。
セルクナムにとっての遠い過去、つまり神話世界のはじまりには、女が男を支配する母権的社会が存在していたとされる。そこでは男は女たちの道具であり、力では敵わない男たちを悪知恵と嘘で支配していた。ある時、女たちの悪知恵と嘘が露呈することになった。男たちが怒り狂い、女たちを皆殺し、そして悪知恵と嘘を排した、「正常」な社会を築くことに成功した。それが今のセルクナム社会だという。これがセルクナム神話の概要と言える。
そして父権制社会が母権制を敵視し、父権制の社会的正当性を周知する祭典こそがハインだった。
そのために男たちは嘘を付かなければならなかった。かつて神話の世界で女たちがそうしたように、男たちは自らが主導権を持つ社会を維持するために、女たちにはなく男だけが持ちうる特権を誇示し、その支配体制の正当性を示そうとしたのだ。
ハインとは、女たちの過去の過ちを糾弾し、そして男たちの正当性を訴えるために催される、長く、奇妙な演劇でもあったのだ。そのために男たちは仮面をかぶり、体をペイントする必要があった。自らが精霊を演じ、人知を超えた存在として、女たちに、男が支配する世界の正しさを説くために。
演劇という第三のハイン
ここでも女たちは気づいている。自分たちが劣っていることを認めろと、男たちは自分たちを嘲って挑んでいるのだ、ということに。こうした芝居をしたところで、彼らの秘密は揺るぎないとたかをくくっているのだ、ということに。
p192, 『ハイン 地の果ての祭典』
嘘を真実にすり替えるには、相当の努力が必要とされる。一般論として、嘘を真実のように見せかけるためには、嘘を重ね続けねばならず、その連続の収拾が不可能になった時、外側の人々にとっては本当でないことが明らかになりながらも、その円環に取り込まれた人たちだけにとっては嘘が日常化してしまいある種の真実と同質のものになっていく。この作用自体は、おそらくはどんな宗教にも、そして創設神話が有効だった時代にも当てはまるだろうが、セルクナムの場合はその作用が日常生活の隅々にまで行き渡っていた。
ではセルクナムの男たちは、女を騙しているという自覚があったのだろうか? 嘘をついているという罪悪感を持ったのだろうか?
その疑問についてはもはや回答を得ることができないが、男たちがハインの秘密を女にひた隠しにし、それを話した者を容赦なく「殺し」ていたことから、少なくとも父権社会の維持のためには必要とされる嘘(必要悪)だとは理解していたと思われる。
そして騙される側だった女たちがその嘘を見抜いていたのかという疑問についても、今となっては確実なことはわからない。しかし著者は最後のセルクナム人たち、特に女性セルクナム人たちとの交流を通してセルクナムの男には絶対に知り得ない言葉を引き出し、女たちは男たちが演じるハインを必ずしもその通りの真実だとは思っていなかっただろうと記している。そこにある矛盾や不備に気がつき、男たちが<演じて>いることも知っていたはずだと。しかしだからと言って、女たちが男たちが構築したセルクナム神話の全てを信じていなかったわけでもなかった。彼女たちは男たちが演じる精霊たちに宿る超常的な力を信じ、畏れ、敬うことを忘れず、セルクナム人としてアイデンティティとなっていた。
それは男たちが精霊となって神話を体現する祭典ハインが、数ヶ月に及ぶものだったことからもわかる。
騙す方も、騙される方も、それぞれが属し共有する社会を維持するためには、その文化と神話を演じる必要があった。ここでハインの第三の役割が立ち現れる。通過儀礼としてのハイン、父権社会維持のための祭典ハイン、そして女たちもともに<演じる>ことで成り立つ演劇としてのハインだ。
男たちが演じる奇妙な格好をした精霊<ショールト>たちが役者なら、女たちもその観客を演じる役者だったのだ。
奇妙な異世界の精霊たち
女や子どもたちと通過儀礼中のクロケテンに一番恐れられているのがショールトだというのは絶対に確かだが、それは出発点であってそれで「話」が終わるわけではない。肝心なのは、「本物」のショールトが存在し、妻の恐るべきサルペンと地下に住み、ともに火をくぐってハイン小屋へと出て来る、ということだ。
p192, 『ハイン 地の果ての祭典』
縞模様のボディペインティングに、奇妙な被り物。
通過儀礼、父権社会維持、そして演劇としてのハインにおいて重要な役割を担うセルクナム世界における精霊ショールトは、成田亨がデザインしたウルトラマンなどに登場する怪獣や怪人の造形を彷彿させる。大きな円柱型の被り物をして両手を後頭部に当てる踊り手マタンや、ハインにおけるコメディリリーフ的な役割を与えられたコシュメンクは、我々がもつ聖霊というイメージよりも、バルタン星人やダダやケムール人といった異世界の住人の姿と結びつく。そして精霊たちが地上の万物を象徴する超越的な存在だとするなら、セルクナム族の精神世界で異彩を放つショールトたちは、やはり異世界の住人といったほうが正しいようだ。
彼らはこの世ならざる地下世界の恐ろしい住人で、ハインの時だけ地上にやってくるとされている。
実際にはショールトも女たちを騙すための装置であり、通過儀礼の対象となる少年たちが乗り越えるべき存在として、大人の男たちが演じているだけだ。そして真実を知らない少年たちは女たちと同じように精霊<ショールト>を恐れながら、ハインへの参加が義務付けられる。狩人としての訓練なども含まれるハインの中で、畏怖の対象である精霊ショールトと戦うことを通して、少年は大人になるために必要な恐怖と向き合うことが求められた。そしてその実像を知った時、女たちには隠され続ける父権社会維持のためのハインの意味を知ることになる。この段階で彼らは少年(騙される側)から大人の男(騙す側)へと移行し、それこそがセルクナム社会のおける本当の通過儀礼になる。
そしてこれまで地下世界からやってくると信じていた精霊<ショールト>を、今度は自分たちも演じることになるのだ。
ではセルクナム族の文化の特異性を美的に表現する、このショールトたちとは何者なのか?
おそらくはその疑問こそが本書を手に取る最大の動機だろう。実際に著者アン・チャップマンも読者の興味の対象を見失うことなく、通過儀礼の祭典ハインをこのショールトたちの役割を通して説明していく。貴重な写真と共にショールトたちの役割が順を追って丹念に解き明かされていく過程は文句なしにスリリングだ。この部分だけでも本書の価値は疑いようがない。
しかしそれでも、ショールトたちの意味や役割の全体像は完全に明かされることはなかった。かつてセルクナムの文化がその独自性を維持できていた頃には40種類ほどのショールトがいたとされるが、セルクナム族にとってはすでに末期だった1923年のハインでグシンデ神父が写真に収めることができたのは10種類ほどで、ハインの詳細をショールトたちの役割から解明しようとすれば必然的にその範囲は1920年代ごろのハインに限定されることになる。
本書で描かれるのはあくまで、セルクナム末期におけるハインについて、だということも間違いない。
そして滅び、秘密が謎になる
「それにしてもなんでみんな私のことをいつも悲しそうだ、と言うのかしら? 私が昔を懐かしんでいろんなことを思い出しているからでしょうね。良いことも悪いことも。悪いことの方が多かったけどね」
p247,『ハイン 地の果ての祭典』
ハインの意味や神話的背景については一次資料を通して明らかにされる<明白な部分>と、二次的な情報を元にした仮説が示す<不明瞭な部分>と、かつては何かがあったはずだが今となっては解明する術が失われた<空白の部分>の三層に分けることが可能だ。そして本書で扱えるのは、無論、著者にとって<明白な部分>と著者による仮説という<不明瞭な部分>に限られる。
しかし同時に、その二層を深く掘り下げることで、自動的に<空白の部分>の第三層の持つ意味が重大な空白として浮上することにもなる。
ハインにおけるショールトの役割は、本書でかなりの部分が明らかにされている。幾何学模様の由来や成分、仮面の役割や意味、モノクロ写真では分からない本当の色彩といった疑問は解決される。それでも本書がセルクナムにとってのショールト、ひいてはハインの意味を完全に解き明かしているとは思えない。著者の怠慢や力不足ということでは決してなく、そこに至るにはあまりに多くのものが、その価値を理解する前にすでに失われてしまっていることが原因に違いない。おそらくは著者が1960年代からフエゴ島の研究を行なっていなければ、その解明範囲はさらに狭まっていたことだろう。
特にあの独特な美的感覚の由来は何なのかについて、わからなくなっていることが残念で仕方ない。そこに彼らは純粋な美を感じてたのだろうか。それともただ父権的権威の象徴として崇めたのか。ブエノスアイレスの博物館で流されていたインスタレーションのように、セルクナム文化の特徴でもあるショールトが美的芸術として今日の我々に消費されるようになったからにはその由来を知りたいとも思った。セルクナムの人々の目にはショールトはどんな風に写っていたのだろう。
そして著者は本書を通して、妙な民俗学的ノスタルジーをひけらかしてはその第三の<空白の部分>について言及することを、意識的に避けているように思える。おそらく研究者としてその部分の解明にも臨んでいるはずで、ある一定の見解は持ち得たのかもしれないが、本著で披露される仮説も明確な根拠の提示が可能なものに限られている。
その理由とはおそらく、著者はセルクナム族という不可思議な幻の民族を、「西洋文明に毒されていない原初的な神秘の民族」とみなすことを拒否しているためだろう。そこには彼女が、セルクナムの女性たちと心を通わすことができたということも関係しているのかもしれない。
かつてフエゴ島を訪れたダーウィンがその先住民を野蛮人と切り捨てたことと、絶滅した民族を理想的な神秘として再発見する行為とは、一見すると正反対の態度にように見えても、安全圏から自分たちの文化を相対的に確認するための道具として彼らを扱っていることには何の違いもない。無論、セルクナム族とその祭典ハインは、彼らのために存在したもので、他の誰のためにあったものではない。
本書で描かれるのは、かつて地球上に存在した、我々から見れば不思議な民族の、その文化の一部と滅びの歴史だと言える。そしてそれは決して遠い過去のことではなく、写真でその断片が確認できるほどに現在と近接した出来事でもあるということは忘れられない。
そして最後に少し意地悪いことを言えば、この本が興味深い理由もまた、彼らが滅び、そして復元不可能なまでに損なわれてしまったからなのかもしれない。それはセルクナム族のように全体で守るべき秘密を持つことができなくなってしまった我々が、自分たちの手でその秘密を解き明かす術を破壊し殺してまでして作り上げた謎を、ただ一人勝手に楽しんでいるだけなのかもしれない。